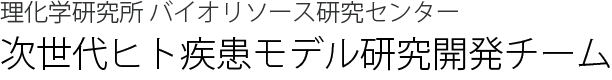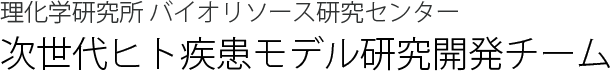プロジェクト
■ 腎疾患モデルマウスの開発と病態解析
慢性腎臓病(chronic kidney diseases, CKD)は日本人の約10人に1人が罹患するといわれる国民的疾患であり、進行すると透析療法が必要な腎不全へと至ります。国内の透析患者は約34万人にのぼり(2022年時点)、社会保障費の負担も大きく、CKDは医療・経済の両面で深刻な社会課題です。このため、早期診断・進行抑制・新たな治療法の開発が急務です。従来、CKDの主な原因は高血圧や糖尿病といった生活習慣病とされてきましたが、近年のゲノム解析の進展により、遺伝的な要因も強く関与することが明らかになっています。遺伝性腎疾患の原因となるバリアントがCKDに罹患した患者ゲノムに認められることもあり、これらはCKDの「潜在的リスク因子」として注目されています。
当チームでは、この遺伝性腎疾患に関連する潜在的なリスクに着目しています。これは、これまで希少疾患とされてきた遺伝性腎疾患の研究が、より一般的なCKDのリスク評価にもつながる可能性があるからです。
そこで私たちは、患者特異的なバリアント情報をもとに、ゲノム編集技術(CRISPR/Cas9)を用いてマウスモデルを開発し(図1)、腎臓の病理組織解析・尿や血液の検査・遺伝子発現解析などを通じて、疾患発症や進行メカニズムを詳細に解析しています(図2)。また、病態再現度の高いマウスモデルに関しては、臨床研究者との連携のもと創薬研究へと展開し、治療法の開発に向けた前臨床基盤の構築にも取り組んでいます。

図1:CRISPR/Cas9システムを用いたゲノム編集マウスの作製概要。ガイドRNAに誘導されたCas9酵素が標的とする遺伝子配列を切断する。切断修復時に疾患バリアントを有するDNA配列が取り込まれ、マウスにノックインされる。

図2:マウス腎糸球体の病理組織解析。HE(ヘマトキシリン・エオジン)染色、PAM染色、Masson’s Trichrome染色、PAS染色等により、糸球体基底膜の構造、メサンギウム細胞の増殖、組織の線維化を評価する。
■ ALS病態に関わるTardbp 3′UTR の発現制御機構
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、随意運動を司る運動ニューロンが選択的に障害される神経変性疾患です(図3)。運動ニューロンの喪失により、筋力低下、麻痺、さらには呼吸不全へと進行します。ALSの患者さんのほとんど(90〜95%)は家族歴がなく、明確な遺伝子変異が見つからない散発性(sporadic)のケースです。そのため、遺伝子変異をもとにした病気のマウスモデルを作ることが難しく、研究における病態の再現が限定的です。
一方で、TDP-43タンパク質の細胞質への異常な凝集は、遺伝背景に関わらず97%以上のALS患者で共通してみられる病理的特徴です。このような共通性の高い分子異常に着目し、私たちはその発現量を調節する仕組みに注目しています。
TDP-43のコード遺伝子(Tardbp)の3′非翻訳領域(3′UTR)には、複数のポリアデニル化シグナルや、TDP-43自身が結合してフィードバック制御する領域が含まれます。私たちは、この領域がTDP-43の発現制御に果たす役割を明らかにするため、3′UTRの一部を欠失させたマウスモデルを作製しました。この欠失により、ホモ接合体マウス胚は原腸形成期で胚発生が停止して致死となります。これは、Tardbp mRNAの発現が大きく低下したことによるものです。さらに、加齢したヘテロ接合体マウスでは、脊髄におけるTDP-43タンパク質の増加、運動ニューロンの減少、軽度の運動機能障害が観察されました(図4)。これらの結果から、Tardbpの3′UTRに存在する制御配列は正常発生に不可欠であると同時に、TDP-43に関連するALS病態にも関与しうることが示されました。

図3:神経変性疾患モデルマウスの作製と病態評価

図4:ALSモデルマウスの脊髄における運動ニューロンの減少。野生型 (A)とALSモデル (B)の脊髄切片におけるKB染色。(C, D) 脊髄のChATの発現(マゼンタ)とDAPIによる核染色(青)。(E)運動ニューロン数の定量評価。
■ マウス亜種を利用した遺伝的多様性の解析
ヒトの疾患発症には、生活習慣や環境要因に加え、ゲノム配列の違い(バリアント)が大きく関与しています。特に炎症や感染防御に関わる免疫細胞では、遺伝的背景によって細胞応答が異なることが知られており、その理解は個別化医療や創薬において大きな意味をもちます。しかし、実験動物であるマウスの研究は通常、基準となる純系系統(たとえばC57BL/6系統)に依存しており、ヒトのような遺伝的多様性を反映させることは困難です。
当チームでは、RIKEN BRCが保有する基準系統等と遺伝的に離れたマウス亜種—Mus musculus molossinus由来のJF1系統—を活用して、遺伝的背景が個体の性質に与える影響を解析しています(図5)。C57BL/6 (B6)とJF1の交配によって得られたF1雑種では、両親由来のアレルが同一細胞内に共存するため、遺伝的な発現制御の違いを直接比較することができます(図6)。本プロジェクトでは、マクロファージを対象としたRNA-seq解析により、免疫応答や代謝経路に関わる遺伝子群でアレル特異的な発現差があることを明らかにしました。特に、解糖系酵素やサイトカイン遺伝子に顕著なアレル特異的発現が観察されており、免疫活性やマクロファージの極性化に影響する可能性が示唆されています。また、アレル発現差が構造多型(SV)と近接している傾向も確認され、SINEやLINEといった反復配列の存在がアレルごとの発現制御に寄与している可能性があります。
今後は、他の免疫細胞や組織にも対象を拡張し、疾患リスクと遺伝的多様性の関係解明、さらには個別化治療の基盤構築へとつなげていくことを目指しています。実験マウスは主にB6系統が用いられますが、異なるマウス亜種(例:JF1、MSM)との交配により、ゲノム配列の多様性を活用した解析が可能になります。当チームでは、異なる亜種由来のF1雑種マウスを用いて、アレル特異的遺伝子発現(ASE)解析や関連するゲノム多型の同定を行い、表現型多様性の原因となるcis調節因子の同定を進めています。

図5:マウスの亜種系統。Mus.musculus domesticusは、西ヨーロッパの野生種を起源とし、Mus.musculus molossinusは、東アジアの野生種を起源とする。

図6:F1雑種マウスを用いたアレル特異的発現解析。共通の転写因子環境下で、B6とJF1由来のアレルの発現量を転写産物のSNPsを基に比較してアレル特異的な発現差を評価する。